CORISM編集長とリセバ総研所長のクルマ放談:2025年9月(前編)自動車販売店と顧客の関係は?

自動車業界で日々生まれる様々なトピックスについて、リセバ総研の“ご意見番”であり日本カー・オブ・ザ・イヤーの運営にも関わっている自動車webサイトCORISM編集長の大岡智彦と、リセバ総研所長の床尾一法の二人が本音で語り合う「クルマ放談」。今月の前半は、オンラインサービスの活用が当たり前の時代に、店頭での顧客コミュニケーションが基本の「クルマの販売方法」はどのように変わっていくのか、語り合いました。

自動車情報メディア「CORISM」編集長

リセールバリュー総合研究所 管理運営者
当記事における発言内容は、床尾一法と大岡智彦の個人的な主観・考察によって構成されています。公式の見解ではございませんのでご注意ください。
目次
クルマのオンライン販売を国内メーカーは実現できるのか?
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
今回は、まず「クルマの買い方」をテーマにしてみたいと思います。最近の新車カーディーラーさんのクルマの売り方って、大岡さん的な視点で何か変化などありますか?
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
基本的には変化はないですね。
カーディーラー網を全国に展開して対面で販売するというスタイルは「崩したくない」というのがメーカーの本音なのかもしれません。
私たちも(メーカーと話して)「そろそろネット販売したらどうなの?」と話してみても、人と人のつながりであったり、販売後のアフターケアだったりを重視しているのだと思いますね。
今の時代はネットで情報を検索して購入したいクルマを検討して、実際にそのクルマを事前に見たり試乗したりしないで買うという人も増えてきているし、知り合いの中古車店の人に聞くと「お店は横浜にあるのに北海道の人から注文が入って、一度も顔を合わせないままクルマを送った」というケースもあるくらい。
購入後のアフターケアは自分で整備工場に電話なりメールなりをすればいいので、手間ではない。実車の確認も写真や動画を活用すればオンラインで完結するし、ネット販売ができる土壌はもうあると思うんです。
正直、僕らの世代でもカーディーラーの営業マンと付き合うのはちょっと面倒くさく感じちゃうし。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
まぁ、そうなってきちゃってますよね。コミュニケーションの手段が(オンライン中心に)変わって、我々オッサンも人との関わり方が変化しましたね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
車検時期になったら「買い替えますか?乗り換えますか?車検に出しますか?」ってアプローチしてきて、車検に出すとなったら「え、乗り続けるんですか?」なんて言われたこともあったりして。
個人的には「(営業マンのサポートが)必要だったらこっちから言うよ!」と言いたくなる。
昔は、営業マンしか持っていない情報というのがあったかもしれないけれど、今はネットを見ればだいたいの情報は手に入るし、営業マンの在り方って変わって行くべきじゃないかなと思うんですよね。
ただ、全国のカーディーラー網は様々な地域に雇用を生み出しているのもまた事実なので、自動車メーカーとしてもこの(現在のディーラーの)仕組みは守り続けたいという意向が強いのかもしれませんね。

-

-
リセバ総研所長 床尾一法
新車の対面商談といえば、以前は顧客側も値引き交渉を期待しての場でしたね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
もう売る側が「定価販売です」と言ってしまえば、値引き交渉の必要もなくなると思います。
結果的に売る側が利益を削る必要がなくなるから、値引きのバッファーを削る分だけ新車価格も安く抑えることだってできるかもしれない。
定価の販売は買う側もメリットがあるんです。
そもそも、これまでの(買う側の値引き交渉を前提とした)新車の商談って「このクルマを好きになって、買いたいんです」というロイヤリティの高いお客さんには(値引きせずに)定価で売って、「値引きしてくれなきゃ他のクルマを買うぞ」という交渉上手なお客さんには値引きして売るという、矛盾した状態になっているんですよ。本当に欲しい人、ユーザーエンゲージメントの高い人に価値を提供するという意味でも、これからは簡潔にモノゴトが進むオンライン販売も選択肢になっていくべきなのかなと思いますね。
韓国・ヒョンデの挑戦から見えてくるもの
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
海外メーカーの話になりますが、韓国ヒョンデは日本への再参入を「Webでの直販」に限定して展開しましたね。
リアルなショールームもありますが、Webショールームも充実させて、商談もオンラインで行えるようになっています。

-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
彼らとしても、そのほうが販売コストを抑えられるじゃないですか。ディーラーを作ったり、フランチャイズを展開して試乗車を共有したりすると、とにかくコストが掛かりますが、それが必要なくなる。
自分たちでクルマを作り、自分たちで売れば、ディーラーに支払うインセンティブも必要なくなるわけです。
情報はインターネット上でいくらでも公開できるし、リモートで商談も可能。
AIを活用すればQ&Aも簡単にできる。実車を見ながら対面で商談する必要はもうなくなってきているんですよね。ヒョンデの試みが成果を生み出せば、自動車販売のあり方がガラリと変わるのではないかと注目しています。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
クルマを買うという特別な行為と煩雑な手続きをコーディネートしてくれるという役割がすべてオンラインでも完結するようになったら、自動車販売の在り方そのものが変わりますね。
現在の状況はどうなんでしょう?成功しているんでしょうか?
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
今のところ成功しているとは言えませんね。
ただ、ノウハウは蓄積されていっていると思うので、これを続けて10年後には大きな変革になっている可能性もあります。
むしろ、輸入車メーカーこそWebを駆使して販売していったほうがいいのではないかと思いますね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
販売網や地場でのつながりが弱い海外メーカーはリスクを回避できますからね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
そう、国産車ほど多くの新車販売店舗を展開することが、とても難しい。顧客とのつながりを醸成するにも時間がかかる。
店を出したとしても、大きな地方都市を中心の限られた店舗展開になって、顧客とのタッチポイントは限られる。小さな地方都市に住んでいると、輸入車を買おうと思っても何十キロもクルマを走らせて、商談しに行かなくてはならないですから。
それに輸入車は「このクルマが欲しい」という指名買いが多い傾向なんだけど、実際のところお客さんのほうがクルマに詳しかったりするわけです。つまり営業マンがクルマの説明をあれこれする必要はなく、結局のところ「いくらで買えるの?」という話だけだったりする。
だったら、輸入車のメーカーやインポーターが全国各地にディーラーを展開するよりも、オンライン販売を中心に展開したほうがコストも抑えられて効率的だと思います。

-

-
リセバ総研所長 床尾一法
ただ、輸入車に多い高級ブランドの場合は、スタッフによるおもてなし、リアルな接客が生み出すホスピタリティのようなものが顧客との関係づくりが重要でもあります。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
お客さんのタイプにもよると思いますね。
人付き合いや会話を楽しみながら買いたいという人も一定数いて、新車ディーラーの仕組みが長く続いているのも、そういう背景があるのかもしれません。
特に高齢者の方は定期的に連絡をくれたり困ったときにはすぐ来てくれる営業マンの存在が大切なのかもしれませんね。地方の新車ディーラーやサブディーラー(自動車整備工場や中古車店などが新車を仕入れて販売する店舗)はそういった価値が提供できているのでしょう。
でも、これから高齢化や都市部への人口集中が加速して、地方の過疎化やサブディーラーの跡継ぎ不足でビジネスが縮小したら、どうなるのかなと。
デジタルネイティブの世代以降は、過疎地に住んでいてもクルマに問題があればオンラインサービスを駆使して自分でどうにかできるのでしょうし、地域に関係なく全国で同じ条件でクルマが買えるオンライン販売は、買う側にとっても売る側にとっても負担が少なく効率的だと思いますね。
販売オンライン化の先にある新車ディーラーの存在意義
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
クルマの売り方・買い方の話の続きとしてメンテナンスの話もお伺いしたいんですが、自動車メーカーさんって補修部品の保有年数や在庫確保の体制って昔と変わらないのでしょうか?
我々のようなクルマいじりが好きな世代は、ディーラーの部品共販(補修部品を一般ユーザーにも分売してくれる窓口)によく通ったものですが・・・
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
さすがにそこまでは把握していないなぁ・・・一部のメーカーでは昔のクルマの部品を再販するという試みは始めていますね。
例えば、マツダのNA型(初代)ロードスターの部品を少量生産して長く乗っているお客さんに提供しましょう、みたいな形ですね。トヨタも始めていますし、日産もやってますね。
長く乗っているお客さんに部品提供やレストアサービスなどで乗り続けられる仕組みを作ろうという動きは見られると思います。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
長く乗り続けるサポートをするというのは素敵な取り組みですね。
私もNAロードスターをいつかは所有してみたいので、もしそんな機会があったらイジり倒すでしょうね。
ただ、ディーラーの立場で見てみると、部品を売ったところで販売台数や売上には貢献しにくいでしょうし、旧車の修理は整備難易度も高くなる。
そう考えると修理対応して長く乗ってもらうよりも、どんどん新車に乗り換えてもらったほうがいいはずです。

-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
もちろんそうだよねぇ。
昔はとにかく買い替えを促進して、古いクルマは下取りして廃車にしていく、というビジネスをやってきたわけです。
でも、最近のクルマはメーカーに関係なくとにかく壊れることが少なくなったと思います。買い替えのタイミングも8年、10年とどんどん伸びている。
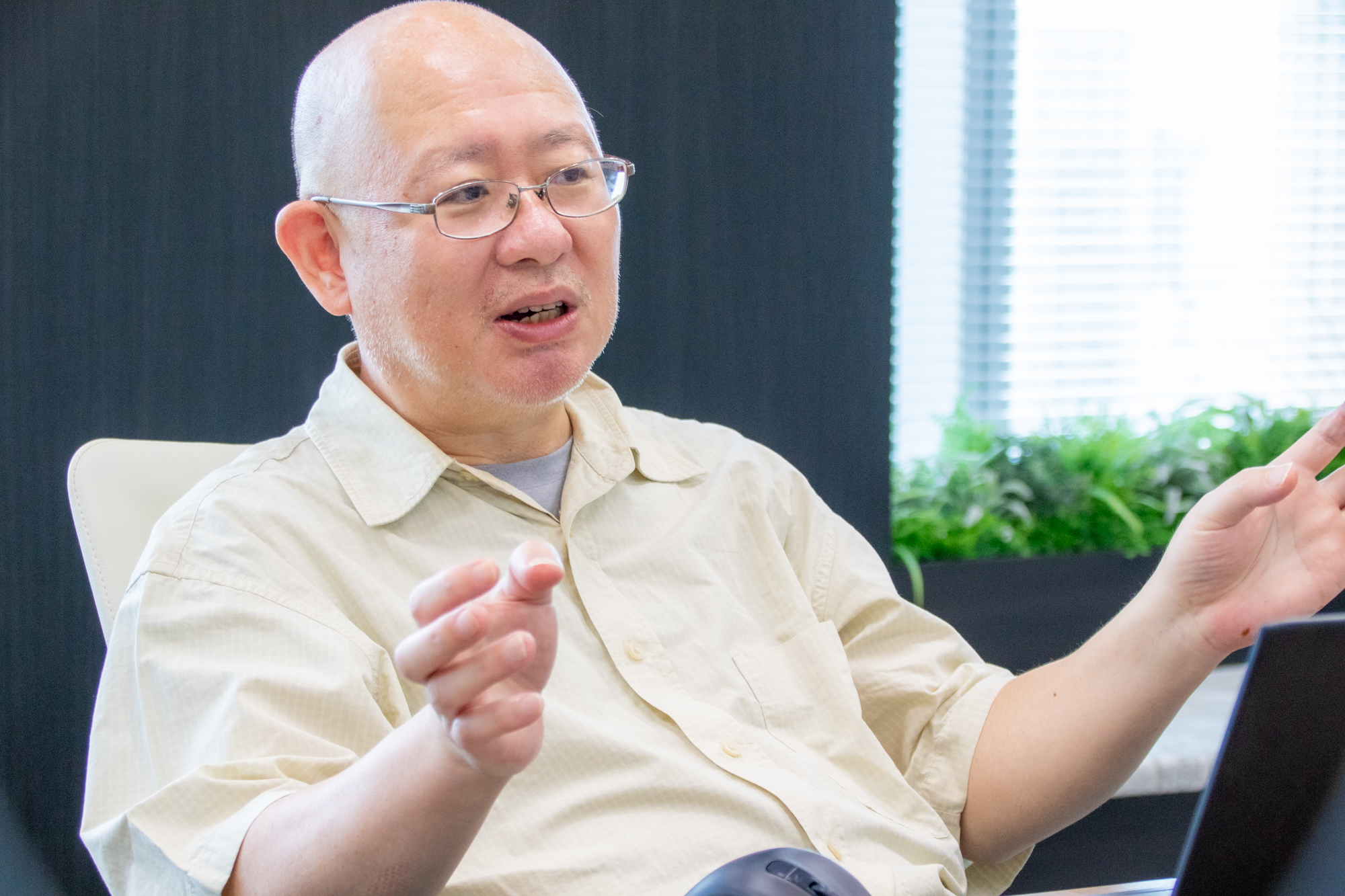
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
はい、買取査定に持ち込まれるクルマのデータを見ても、保有期間が年々伸びてますね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
そういう視点で考えると、カーディーラーの収入源はクルマを売ることよりもサービスを提供する方向にシフトしていっていますね。
例えば法定定期点検を含めたメンテンスパッケージを提供してお客さんとの接点を維持しましょうとか。トヨタの「GRガレージ」は、新車の販売だけでなくパーツ販売や取り付けなどでも収益化しています。
「上がり続けるクルマ価格」と「横ばいの所得」の狭間で
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
10年超えても故障なく乗り続けられる、乗り続ける人が増える、となると、これからの新車販売台数ってどう変化していくんでしょうね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
すでにもう伸び悩んでますしね。ここ数年はコロナ禍以降の供給不足や不正問題といった影響もあるので判断が難しいですが、人口の減少や高齢化を考えると厳しいかもしれません。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
新車の販売あっての中古車流通ですから、その影響は大きいですね。
円安の影響もあって日本から良質な中古車がどんどん海外に流出していますし、その結果として日本の中古車の品質が低下してしまうのではないかという懸念もあります。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
最近の中古車相場ってかなり高額になっているイメージだけど?
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
上がっています。中古車として最もお手頃感のあるクルマ、品質が良くて買いやすい200万円台のクルマというのは、海外により高値で買われていってしまう状況です。
それまで仕入れていた中古車の品質と同等のクルマを仕入れようと思っても(海外需要のために)流通価格が上昇しているので、仕入れ担当者も品質維持と魅力的な価格のバランス取りに苦労しています。

-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
物価の上昇を加味しても、クルマは高価になりましたね。
国は「所得を上げましょう」「給与が上がりました」とアピールしていると認識しているですけど、でも実際に所得が増えている人は一部の人たちかなと個人的には捉えてます。
殆どの人たちの給与所得はほぼ横ばいじゃないか?という状況の中で物価はどんどん上がっている。生活が逼迫して高い買い物をする余裕なんてなくなっているんじゃないかと思いますね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
最近では比較的安価な軽自動車の需要が高まっていて、10年落ち前後の軽自動車でも買取査定の価格が上昇しています。
低年式の中古車であっても相場が上がっている状況です。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
そうですよね。
これは個人的な感想だけど、先日ダイハツ ムーヴのモデルチェンジが発表されたときに、いわゆる「子離れ世代」をターゲットにしていて実際に売れているという話を聞いて、「子離れして生活にちょっと余裕ができたから、少しいいクルマを買おう・・・じゃないんだ」と。
すごく守りの生活に入ってきているわけです。
老後に年金じゃ生活できないかもしれないし、税金も物価も上がり続けると考えるともう恐ろしくて、「いいクルマを買おう」なんて言っていられないんでしょうね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
私も個人の意見ですが、消費が落ち込んでいるとは感じますね。
アルファードの買取相場が暴落しているのも買う人が減ったという事情もあってのことだと思います。
リセバ総研の発行した「リセールバリュー白書」でも、これまで5〜6年落ちが買取査定のボリュームゾーンだったものが、最近は7〜8年落ちになっています。さきほども話に出ましたが、クルマを所有する期間がのびているんですね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
消費者は不測の事態に備えて財産を溜め込むモードに入ってるのかもしれませんが、都市部に住んでいたらクルマの必要性も薄れるので「クルマは要らないよね」という判断をする人も多いと思います。
実際、私が住んでいるマンションの駐車場なんて、新築当時はすぐに満車でしたが、30年も経つと約6~7割くらいしか駐車場が埋まらない状態。管理費はかかるけど駐車場代が入ってこないので、理事会でも問題になるくらい。
こうしたケースは、都市部によくあるみたいですしね。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
私のクルマは軽自動車なので、都内に住んでいると一番大きな維持費は駐車場代。
クルマを手放せば毎月数万円の出費がなくなるので、相当に影響は大きいですね。
今年で(購入から)5年目。
おそらく来年からリセールバリューが大きく落ちる可能性があるので、高齢ながら幼児の子育てが一段落する今、手放すか迷いどころですね。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
ハイトワゴンならば、結構高値がつくんじゃないですか?10年乗っても値段がつくでしょう。
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
そうなんですよ。
先程も話しましたが軽自動車の需要が伸びていて、10年落ちでもクルマの状態によってはリセールバリューが維持できます。
軽自動車は新型が出ても大きな差が出ることもなくなったので、旧型の価値が急に落ちるということはないですね。車種や状態にもよりますが。
自動車ビジネスはこれからどう変わっていくべきか
-

-
リセバ総研所長 床尾一法
さきほどの新車ディーラーの話にもつながりますが、これからの自動車販売店と顧客の関係はどのようなスタイルになって行くと思いますか?
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
私なんかは直接話したり交渉したりするのが面倒に感じることもあるし、忙しいときにお店から電話がかかってくると億劫に感じてしまう。
昔はそれが普通だったから気にならなかったけど、今はメールやLINEとかいろんな連絡手段ができてきたから、電話が不快に感じるときもある。
最近の電話って怪しげなところから無断でかかってくることも多いから、余計に電話に対して警戒感を抱いてしまいますね。

-

-
リセバ総研所長 床尾一法
電話よりもLINEで連絡をくれたほうが対応しやすいという方も多いでしょうね、いまは。
私も(LINEの)企業アカウントの友達追加に抵抗がなくなりましたね。気軽かつ削除も気兼ねがないですし。
-

-
【自動車のプロ】大岡智彦
とはいえ、営業マンと直接会って話すことも自動車販売店の価値ですしね。
連絡も電話で話してもらえる方がいいと感じる方もたくさんおられるはずです。
一方で、ネットに慣れてしまっている人たちにとっては違和感を感じる方も多いでしょう。今の時代、タクシーを呼びたいときでも電話じゃなくて配車アプリを使ったほうが便利な世の中ですから、自動車業界もオンラインの接点を駆使した営業をしていかないと時代に取り残されてしまう。
今後は販売店に接客を期待してクルマを買う従来のスタイルと、スマホでも契約できるくらい簡潔なプロセスでオンラインで買うスタイルと、2極化が進むのではないかと思います。
